荊楚の民族は月の元 を下弦に定めていた

久留米市田主丸町二田(ふたた)月読神社の神紋は月に三つ星紋だが、月の向きに意味があるとすれば下弦の月になる。
ずっと気になっていたところ、このような記述を見つけたのでメモ。
月齢23~25の頃を月初
『儺の國の星』復刻版第2版 『儺の國の星 拾遺』第2版
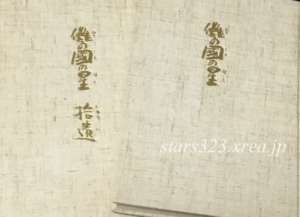
『儺の國の星』復刻版第2版と『儺の國の星 拾遺』第2版が那珂川市より出ている。
第二版は用紙が変わり厚みが増し、表紙も簡易になっていた。
奥付。
郵送にも対応されている。
興味のある方は那珂 ...
皇太子はいつの世も天皇に奉るべき暦書の編纂と暦日の観測が業務だった

太子星の名もあった。中世は上人の托鉢の椀の形を想像し、佛壇に供うべき器に見たてたかもしれない。又皇太子はいつの世も天皇に奉るべき暦書の編纂と暦日の観測が業務であった。この星が登る頃は立春であり、又春分であった。
(『儺の國の星拾 ...