続・荊楚の民族は月の元を下弦に定めていた

『儺の國の星拾遺』p.204に「荊楚の民族は月の元を下弦に定めていた」とある。
月齢23~25の頃を月初めとしたという。
以前、月読神社(田主丸町二田)神紋が下弦の三日月だったことから二十三夜待ちとの関連で紹介した ...
日本も蒙古も全く同じ時代に全く同じ趣旨でAndromeda が、春分の正午に太陽と上下に並ぶ年に改元した事実をよく考察せねばならない
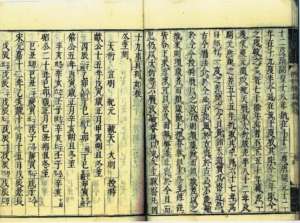
日本人も蒙古人もその遙(はる)かな祖先はAndromeda(アンドロメダ)大星雲を拝していた。神代紀に出る高木神(**たかきのかみ)がそれである。これを大嶽(たいがく)と名付けていた。
日本は文永元年、蒙古は ...
文永への改元理由は太陽と高木星が春分に同時南中したことだった & 同時南中の計算法

1264年に日本は年号を「文永」に改元しているが、その理由はアンドロメダ銀(*)河と太陽が同時に南中したこととする話がある。
日本人も蒙古人もその遙(はる)かな祖先はAndromeda(アンドロメダ)大星雲を拝していた。 ...