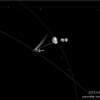日本も蒙古も全く同じ時代に全く同じ趣旨でAndromeda が、春分の正午に太陽と上下に並ぶ年に改元した事実をよく考察せねばならない
日本人も蒙古人もその
遙 かな祖先はAndromeda 大星雲を拝していた。神代紀に出る高木神 がそれである。これを大嶽 と名付けていた。
日本は文永元年、蒙古は至元元年と改元したその年は、春分の正午にAndromeda の中心が重なった。西暦一二六四年であった。
(中略)
日本も蒙古も全く同じ時代に全く同じ趣旨でAndromeda が、春分の正午に太陽と上下に並ぶ年に改元した事実をよく考察せねばならない。(『儺の國の星拾遺』p.22~p.23)
〝日本と蒙古が同じ理由で同時改元した〟と筆者は言う。
そしてその事実をよく考察せねばならないとも。
両国が暦を策定する共通のシステムを持っていたというのだろう。
そしてそのシステムは中東がルーツだと暗に言っている、と私は受け取った。
というのも、蒙古(モンゴル帝国)時代にイスラム天文学の観測技術を使った授時暦という精密な暦が作られているからだ。
13世紀にイスラム天文学が入ってきた時、それを受け入れる下地があったからこそ、このような暦が出現したと考えることが出来ると思うからだ。
中東の星読みの氏族が大陸ルートと海上ルートで日本にやって来た、と筆者が繰り返し述べていることとも合致する。
さて、今回私が考えたいのは、授時暦編纂者の一人郭守敬が荊州の人だということ。
荊州と言えば、「荊楚の民族は月の
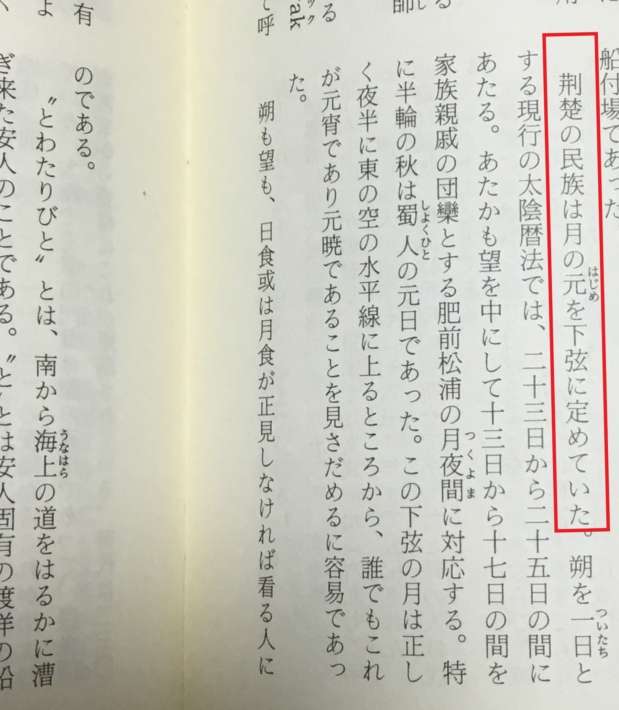
月の観測に長けた独自の暦を持っていた荊州人。
その一人郭守敬が、13世紀にイスラム天文学を元にした授時暦を作ったというのは、それまでの下地があったからではないかと思う。
そしてそのことは、日本古来の暦のシステムと無関係ではないと思うのだ。