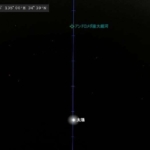続・荊楚の民族は月の元を下弦に定めていた
『儺の國の星拾遺』p.204に「荊楚の民族は月の元を下弦に定めていた」とある。 月齢23~ ...
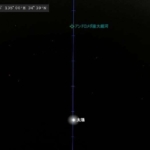
文永への改元理由は太陽と高木星が春分に同時南中したことだった & 同時南中の計算法
1264年に日本は年号を「文永」に改元しているが、その理由はアンドロメダ銀(*)河と太陽が ...

惑星の日面通過の話をした
ご依頼は「星の話が聞きたい」だった。 何が知りたいか尋ねると、「何にもわからないから何でも ...
ステラナビゲータとカシミール3Dを使って星の伝承を読んでいます